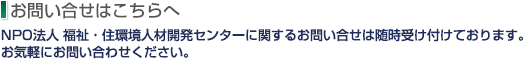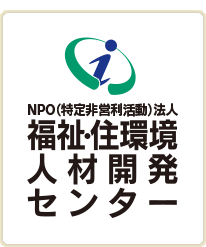2003年9月11日(土) 場所:東京しごとセンター
精神科医の立場から、医学的に「認知症」について解説。
環境といっても単にケアだけではなく医療との密接な関係も必要。また自分の能力をお金で売っているプロのケアと家族のケアは仕分けることが大事。要介護4や5の高齢者の介護をしている家族の報酬は年収750万円ともいわれる。そういった家族の工夫に共感し全人的なケアプランを考えたい。できないこと(Ex.転倒しないためには…など)に注目するケアではなく、その人が持っている力を把握し援助していくケアを目指したい。お年寄りは疲れているわけではない、生きる意味を求めている。
よく聞く「問題行動」などは、行動の障害であって問題行動とは言わない。
まわりが「問題」にしている。インフォームドコンセントで説明と同意を得ることは(動物的)安心感がある。好むか好まないかと選択の自由は必要。認知症高齢者に対しほとんどの事が了解なしに始まっていないだろうか。「あなたは『怒り』をどのように表現していますか?」などについてあらかじめ知り得ておくことも大切。認知症高齢者の問題行動は何かへの挑戦であると受け止めよう。
オーストラリアで実践されているダイバージョナルセラピー:DTをスライドで解説
「オーストラリアでは、高齢者福祉施設でのアセスメント(利用者の援助計画を作成するための情報収集と課題分析)を重視しています。その人がどんな生活を送ってきたのかを大切にし、ふさわしい環境を提供するというケアを実践しています。DTはひとり一人の価値観を把握し、その人自身がより生活を楽しめるように支援するケアの専門家です。例えば、ポストを求めて徘徊する認知症高齢者の為に庭にポストを設置したり、食事の時には食卓の周囲に花を飾るなどテーブルセッティングにも気を配ります。」と語る芹澤氏。まずはセラピスト自身が生活を楽しむ積極的な姿勢が必要であるようだ。
日本で取り組まれているDT、ドールセラピーについても解説。
「『たあたん』という赤ちゃん人形を使ったドールセラピーについても紹介します。この赤ちゃん人形は様々な高齢者施設で愛されています。ある施設では、認知症を伴った女性が、たあたんを抱いているうちに表情が柔らかくなっていきました。施設での高齢者の皆さんの表情をお見せするために、たくさんのスライドをお持ちしました。」との芹澤氏の言葉を受け、洋服を着せてもらうたあたん、抱っこしてもらうたあたんなどが紹介された。どのスライドの高齢者の方も和らいだ表情で、1体のドールが愛情という感情を思い出させてくれているようだ。